
週末の友人の結婚式でピアノを演奏していた先輩(とお呼びするのは恐れ多い大先輩)に
「素敵でした。相当弾けるんですね」と感想を伝えたところ、
すぐさま「30時間は練習したからね」という答えが返ってきたのが印象的で、少し考えています。
(注)その方はプロのピアニストではありません。
絶妙な練習量と計画性
普段めちゃくちゃ忙しい先輩が『30時間』という明確な時間を積み上げている計画性に、まず唸ってしまった。
とっさの返事として『30時間』という極めて具体的な数字が出てくるということは、それだけ意識して練習をしてきたということなのでしょう。
練習期間は分からないけど、仮に1~2ヶ月として、30min~1h/日。
ほぼ毎日この時間を確保するのは、簡単なことじゃない。
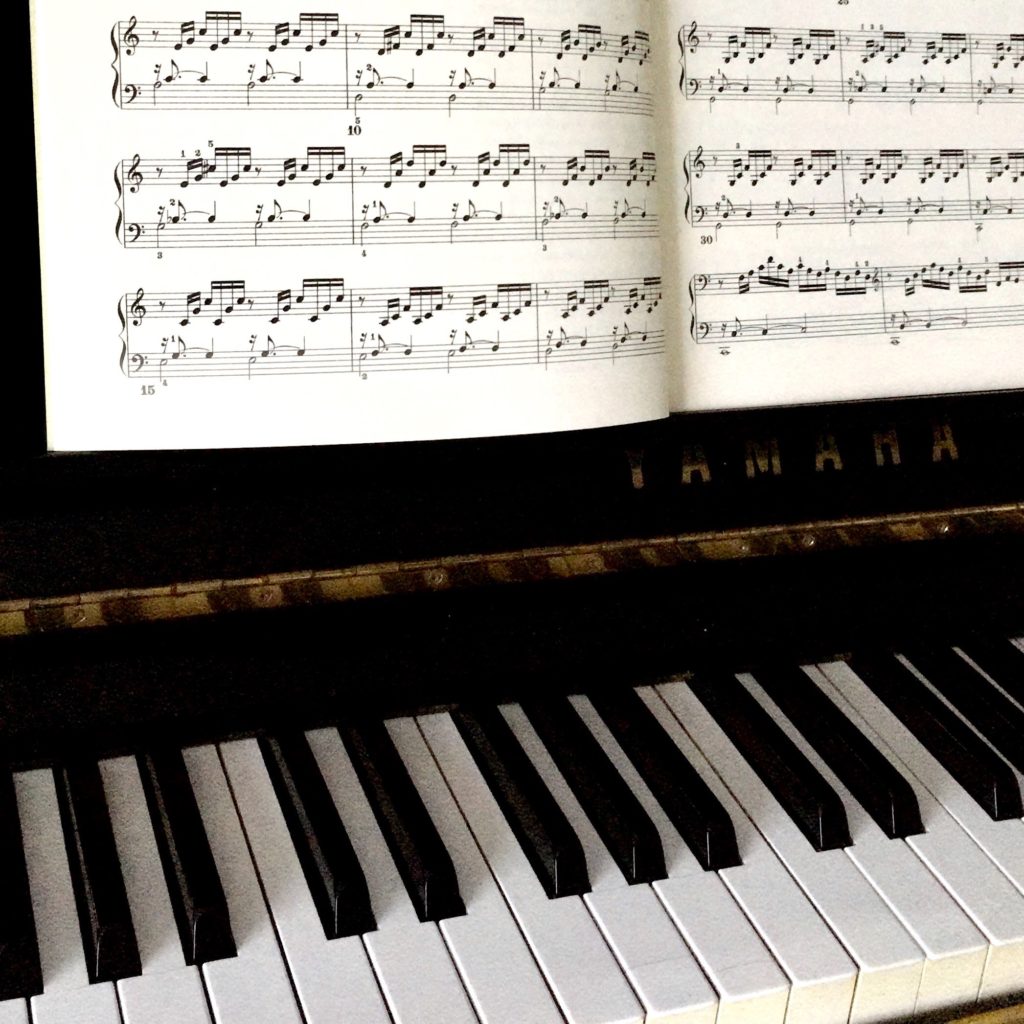
そして『30時間』というのは、絶妙な練習量だと思います。
ピアノに限ったことではなく、もともとある程度の技量がある人が一つのことをこなせるようになるまでの時間として、30時間。
突き詰めた表現を求めるならば、それ以上の時間が必要になることは言うまでもありません。
しかしながら、限られた時間の中でしっかりと結果を出すというミッションにおいてこの【30時間】は一つの目安になるのではないかと感じました。
例えば、3時間で1冊の本を読めるとすれば10冊分の時間。
ある特定のテーマに絞って10冊の本を読めば、相当のアウトプットが可能になります。
一つのプロジェクトに3時間/日コミットするとして、10日間。
10日間あれば何らかの明確な結果を出せるでしょう。
練習は計画的に
自己認識と状況把握。
①自分がどれくらいの力量を持っているのか
②それを達成するにはどれくらいの力が必要なのか
そして、
②-①=必要な努力
必要な努力(練習量)をどうやってスケジュールしていくかという計画性。
とても基本的なことかもしれませんが、
何かをできるようにするための基本は、こうした姿勢なんだ思います。
振り返ってみると、僕が臨書に取り組む際には、
「どれくらいの枚数(量・回数)書いたか」という数値を目安にすることが多かったのですが、
最近は #蘭亭序 を勉強しています。いくつか文字をピックアップして点画や偏とつくりを確認してから、さていよいよ今日から本文を #臨書。蘭亭序は全部で324字。半紙一枚に6字ずつ臨書すると55枚で全臨。2日で1周のペースでまず10日。そのあと1日1周ペースにもっていきます。目標は15日間で10周です。 pic.twitter.com/finPcKuVfd
— 小杉 卓@書家 (@takuksg13) May 23, 2018
臨書のペースを作る。
今日は蘭亭序の前半分。まずは2日で全臨のペースで5回。それからは1日1回全臨するペースを作って5回。 pic.twitter.com/yEsubikOrT— 小杉 卓@書家 (@takuksg13) May 24, 2018
このやり方だと、
一見すると定量的ではありますが、けっこうな場合においてパワープレイになる。
(昨日できなかった分も含めて今日2倍やる、など)
これ、例えば夏休みの宿題の計画とかでも言えると思うんですよね。
数学 〇〇ページ/日、などという計画を立てて、何日分もためていくパターン。
それよりもきっと、
数学 30分/日、なんだと思います。
ということで、
『時間』という絶対軸をもってプロジェクトを進めていくという、
とても参考になる週末の出来事だったのでした。
小杉 卓
こんな記事も書いてます