中学校でも高校でも、大学でもいい。
皆さんにとって自分の学生生活をふと思い出す瞬間はあるだろうか。それはどんな場面だろうか。
僕にとってのその『場面』は本棚からある本を手に取ったときだった。その本のタイトルは「羊をめぐる冒険」。村上春樹さんが描いた長編小説だ。僕は村上春樹さんが書く本が(小説もエッセイも)大好きなのだけど、そのときはこの本の内容を全く知らずに、本棚からふと手に取った。冒頭を軽く読み進めているとこんな文章に巡り合う。
その年の秋から翌年の春にかけて、週に一度、火曜日の夜に彼女は三鷹のはずれにある僕のアパートを訪れるようになった。彼女は僕の作る簡単な夕食を食べ、灰皿をいっぱいにし、FENのロック番組を大音量で聴きながらセックスをした。水曜の朝に目覚めると雑木林を散歩しながらICUのキャンパスまで歩き、食堂に寄って昼食を食べた。そして午後にはラウンジで薄いコーヒーを飲み、天気が良ければキャンパスの芝生に寝転んで空を見上げた。水曜日のピクニック、と彼女は呼んだ。
「ここに来るたびに、本当のピクニックに来たような気がするのよ」
「本当のピクニック?」
「うん、広々として、どこまでも芝生が続いていて、人々は幸せそうに見えて……」
彼女は芝生の上に腰を下ろし、何本もマッチを無駄にしながら煙草に火を点けた。
「太陽が上って、そして沈んで、人がやってきて、そして去って、空気みたいに時間が流れていくの。なんだかピクニックみたいじゃない?」
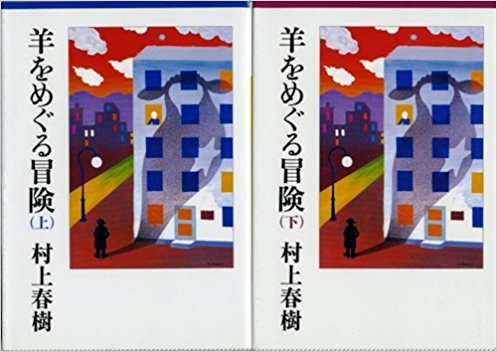
(村上春樹「羊をめぐる冒険(上)」より)画像;Amazon
ああ、大好きな村上春樹さんの文章が、大好きな大学のキャンバスを語っている。とても村上春樹的に。そしてICU的に。そして冒頭に書かれている通り、まさに今くらいの寒い季節なんですよ。寒空の下、コートを着たまま太陽の日を浴びて広い芝生に腰を下ろす。すると枯れた芝生がお尻や、寝転がったりすると背中から頭から体中につくわけです。これをバカ毛と呼んでいたのです(芝生一帯が『バカ山』という呼称だったから)。
もう一つ、村上春樹さんの本の中の言葉で印象に残っている言葉があって、初めてその本を読んで10年以上たった今でもときどき思い出す。
「ノルウェイの森」。おそらくは「羊をめぐる冒険」よりも知っている人は多いと思う。この本に出てくる長沢さんは主人公の住む寮の先輩で、東大法学部、のちに外務省というエリートだ。
永沢という男はくわしく知るようになればなるほど奇妙な男だった。僕は人生の過程で数多くの奇妙な人間と出会い、知り合い、すれちがってきたが、彼くらい奇妙な人間にはまだお目にかかったことはない。彼は僕なんかはるかに及ばないくらいの読書家だったが、死後三十年を経ていない作家の本は原則として手に取ろうとしなかった。そういう本しか俺は信用しない、と彼は言った。
「現代文学を信用しないというわけじゃない。ただ俺は時の洗礼を受けていないものを読んで貴重な時間を無駄にしたくないんだ。人生は短い」
「永沢さんはどんな作家が好きなんですか?」と僕は訊ねてみた。
「バルザック、ダンテ、ジョセフ・コンラッド、ディッケンズ」と彼は即座に答えた。
「あまり今日性のある作家とはいえないですね」
「だから読むのさ。他人と同じものを読んでいれば他人と同じ考え方しかできなくなる。そんなものは田舎者、俗物の世界だ。まともな人間はそんな恥ずかしいことはしない」
(『ノルウェイの森』より) 画像:Amazon
『時の洗礼』という言葉が、とてもリアルに心の中に響いたのを覚えている。それは、長沢さんの読書への姿勢に共感するということだけではなくて、おそらくは僕自身がクラシック音楽と書道に取り組んでいるということと無関係ではないと思う。
さて前置きが長くなったが、このブログの本題はここからだ。
200年、300年、あるいはそれ以前に書かれた音楽を今の時代に演奏して多くの人を魅了するクラシック音楽というのはやっぱりすごいし、西洋圏に限らず世界中に広がった文化というのは、いわゆるクラシック音楽が筆頭ではないかと思う。長沢さんの読書的に音楽をジャンル分けするならば、『時の洗礼』を受けた音楽なわけだ。そしてここまで世界的にクラシック音楽文化が広がったのは、その様式が「言語」ではなく「音」だからではないかと思う。楽譜に書かれた音を演奏すれば、老若男女、どんな言葉を話す人であっても同じ音楽を奏でることができる。

さて書道には、古代中国の歴史と共に2,000年、3,000年の歴史があると言われる。しかし、クラシック音楽と決定的に違う点はその芸術の源泉が漢字を主とした「言語」であることだろう。とくに古典的な書については、そこに記述されている内容を理解できる人は限られる。漢字を使っている東アジア文化圏の人であっても、過去と今との文法の違いに悩まされることだろう。
それゆえ、過去に書かれた書を今の時代に書いて(臨書して)、どれだけの人を魅了することができるかは大きな疑問なのだ。もしかすると、書に取り組んでいる人なんかであれば、それを観ていて楽しいかもしれない。技術的な視点や、学んだ知識があるから。でも、多くの人にとって読めない・意味の分からない作品を観て楽しいかどうかといわれれば、決してそうではないだろう。残念ながら。
いまの時代を生きる人を魅了するためには、今の言葉を書くというのは必要だと思う。しかし「書」という範疇の中で表現しようとするならば、古典の脈絡を書いた書には、ほとんどの場合「力」がない。だから、理想的な書の在り様は、古典で力を磨きつつ今の言葉を語ること。つまり、「時の洗礼」を受けた書の力をもって、今の言葉を語ることが必要だ。

クラシック音楽に取り組んでいる人も、きっと自分の音を磨きながら、今この時代に奏でる音楽を模索しているはずだ。音楽という文化をお手本にしたい。音のない書道、言葉のない音楽。それぞれが交わる点があるとしたら、どんな芸術になるだろうという想像は尽きない。


