シンプルな線こそ技量が問われる。
古典を臨書していると
「一」とか「十」はかなりの頻度で出てくるけれど
複雑な漢字よりもよほど難しい。
でも、作者はちゃんと書き分けている。
一本の線の中にいろいろな表情がある。
例えばこの「一」という字。
(藤原行成「白氏詩巻」より)
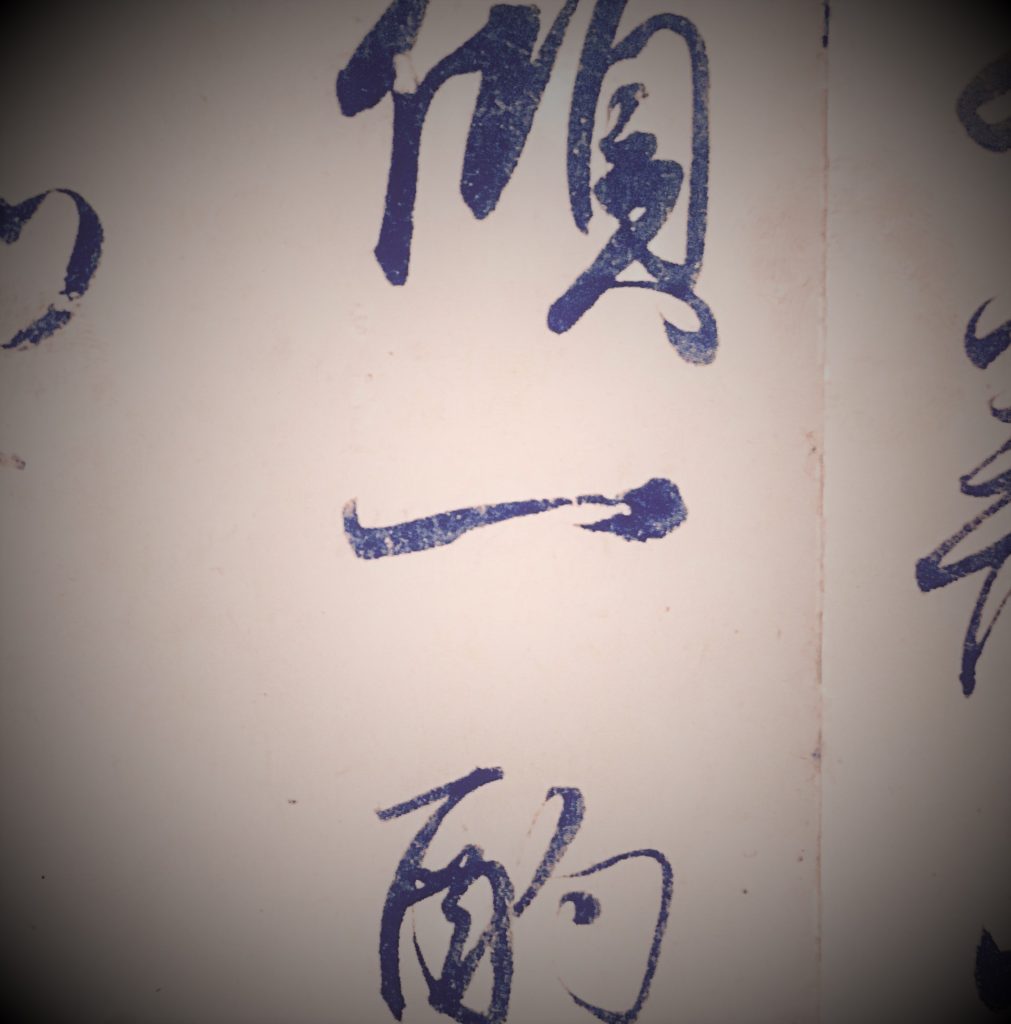
起筆から1/3くらいまでは太さを保ったまま筆を運び、
そこから一気に力を抜いている。
おそらくここで運筆のスピードも速くなっているだろう。
終筆では筆の圧力をかけたままに左側に筆を倒して、
起筆のポイントに向かうように筆を収めている。
実物の大きさはせいぜい2cmほど。
このわずかな線の中にこれだけの表現を詰め込めるなんて、
見事というほかない。
書道に取り組む中で、
一見すると画数の多い感じを難しく感じる方も多いと思う。
でも、画数が多いということはその分、
多くの線でその漢字の構成を支えることができる。
仮に一本、バランスを崩した線があっても、
その他の線の書きようによっては、文字全体としてのバランスを整えることができる。
画数が少ない文字の場合はこうはいかない。
「一」であれば一本、その線がその文字のすべてだ。
そこに技量のすべてが現れる。